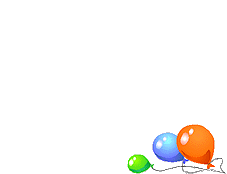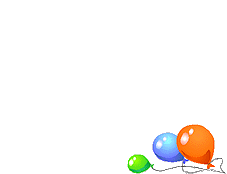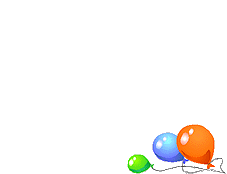| NO |
写 真 |
概 要 |
| 1 |
 |
八幡社である。海津城(後述)を出た武田軍は二手に分かれ、一隊は東の山を迂回して妻女山へ、本隊はここに陣を構えて追い出される上杉軍を待ち構えた。右手の看板の後ろや左手に土塁があるのがご覧頂けよう。これは武田軍の桝形陣形の跡である。当時のまま残っていると聞く。
|
| 2 |

|
こちらが上杉謙信の軍旗『毘』の旗である。上杉謙信が信仰した毘沙門天の一字を旗にしたもの。戦場において戦の神・毘沙門天の加護のもと、上杉軍将兵は一致団結して水火も辞さない勇猛果敢な働きをした。この他上杉軍では突撃の合図となる『龍』の旗も用いた。『龍』は乱れ龍を意味し、突撃の時に先頭に押し立てて進む。精強な兵卒に抜群の将才を持った大将。上杉軍の『毘』と『龍』の旗はそれを見た敵兵に戦わずして恐怖心を引き起こしたという。
|
| 3 |
 |
こちらが武田信玄の軍旗で有名な『風林火山』の旗である。別名孫子の旗とも呼ばれ、「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」の句が染め抜かれている。これは『孫子』の軍争篇で軍隊の進退について書かれた部分にある「其疾如風、其徐如林侵掠如火、知難如陰、不動如山、動如雷霆」即ち、「其の疾(はや)きこと風の如く、其の徐(しず)かなること林の如く、侵掠すること火の如く、知りがたきこと陰の如く、動かざること山の如く、動くこと雷霆(らいてい)の如し」からの引用である。もとは鮮やかな紺色の絹布に金泥で書いていた。字は武田家の菩提寺・恵林寺の禅僧・快川招喜(かいせんしょうき)の筆によるものだとか。因みにこの人は織田軍によって武田家が滅亡した時に、恵林寺において「心頭滅却すれば、火もまた涼し」と言い捨て焼死している。信玄の旗にはこの他、南無諏方南宮法性上下大明神」という旗もある。「風林火山」と共に武田軍の象徴。
|
| 4 |
 |
こちらが有名な銅像。武田軍別働隊が八幡原に到着し挟撃されることとなった上杉軍は、前面に展開する武田軍本隊の真ん中を突き破って北の善光寺に向けて撤退。その時に謙信と信玄が一騎討ちに及んだという逸話に基づくもの。上杉謙信は紺糸縅(こんいとおどし)の鎧に萌黄緞子(もえぎどんす)の胴肩衣(どうかたぎぬ)、金の星兜に立烏帽子白妙(たてえぼししろたえ)の練絹で行人包(ぎょうにんづつみ)、長光(ながみつ)の太刀を片手に名馬・放生(ほうしょう)に跨がって戦況を睨み、両翼に広く展開した武田軍の中で本陣が手薄になったのを見て、旗本数騎と共に突撃しました。一方の信玄は諏訪法性の兜に黒糸縅の鎧、その上には緋の法衣を身に纏い、軍配を振りながら劣勢に崩れ立つ味方の兵を鼓舞していた。この信玄の姿を見た上杉謙信が単騎で駆け寄りざまに太刀を一閃、信玄はかろうじて軍配で受け、続く二の太刀で腕を、3の太刀で肩を切られ。戦後この軍配を調べたところ刀傷が7カ所に及んでおり、この一騎討ちの跡を世に「三太刀七太刀の跡」と呼ぶ。八幡社の主殿の横に碑が立っている。
|
| 5 |
|
信玄と謙信の一騎討ちの最中、信玄危うしと見た中間頭の原大隅(はらおおすみ)は、側にあった信玄の持ち槍「青貝」(青貝の柄の槍)を手に謙信目がけて突き出した。しかし槍は鎧の肩の上に外れたので、続いて右上から肩を目がけて斜めに振り下ろしたが、これも外れて馬の三途(背中)を叩き、馬は驚いて跳ね上がり謙信を乗せてその場を去ったため、信玄は九死に一生を得た。
原大隅は騎馬武者を逃したことを悔しがり、腹いせに側にあったこの石を槍で突き通したと言われている。以後この石は執念の石と呼ばれるようになった。見ると確かに穴が開いている。しかし本当に槍で突き通したものかどうかは不明。
|
| 6 |
 |
こちらは逆槐(さかさえんじゅ)と呼ばれる古木。ここに本陣を置いた信玄は、土塁を築き矢来を組み盾をめぐらせて防備を固めた。その時に土塁の土止めにと自生していた槐で、根を上にして杭を作り打ち込んだ。それが芽を出し400年を経て大きくなったのが、この木だと言われている。しかし、川中島合戦の様子を見た木だと思うと感慨もひとしお・・・。
|
| 7 |
 |
こちらは首塚。合戦の後、海津城主の高坂弾正昌信が敵味方の区別無く死体を集め、手厚く葬った塚だそだ。川中島合戦の戦死者は戦国時代でも飛び切りの6千余人。ここら中が首の無い死体だらけだったのでしょう。この処置に感激した謙信は、後に塩不足に悩む武田氏に対し、「我信玄と戦うもそれは弓矢であって魚塩にあらず・・・」と言って塩を送ったという逸話が残っている。しかしこれは後世・江戸時代の創作らしい。昔はこの辺りに首塚がゴロゴロしていたようだが、現在ではこの首塚とここから東南約180メートルのところにある首塚の二つが残るだけのようだ。首塚の上の碑は、戦前の陸軍の御偉いさんが建てたもの。
|